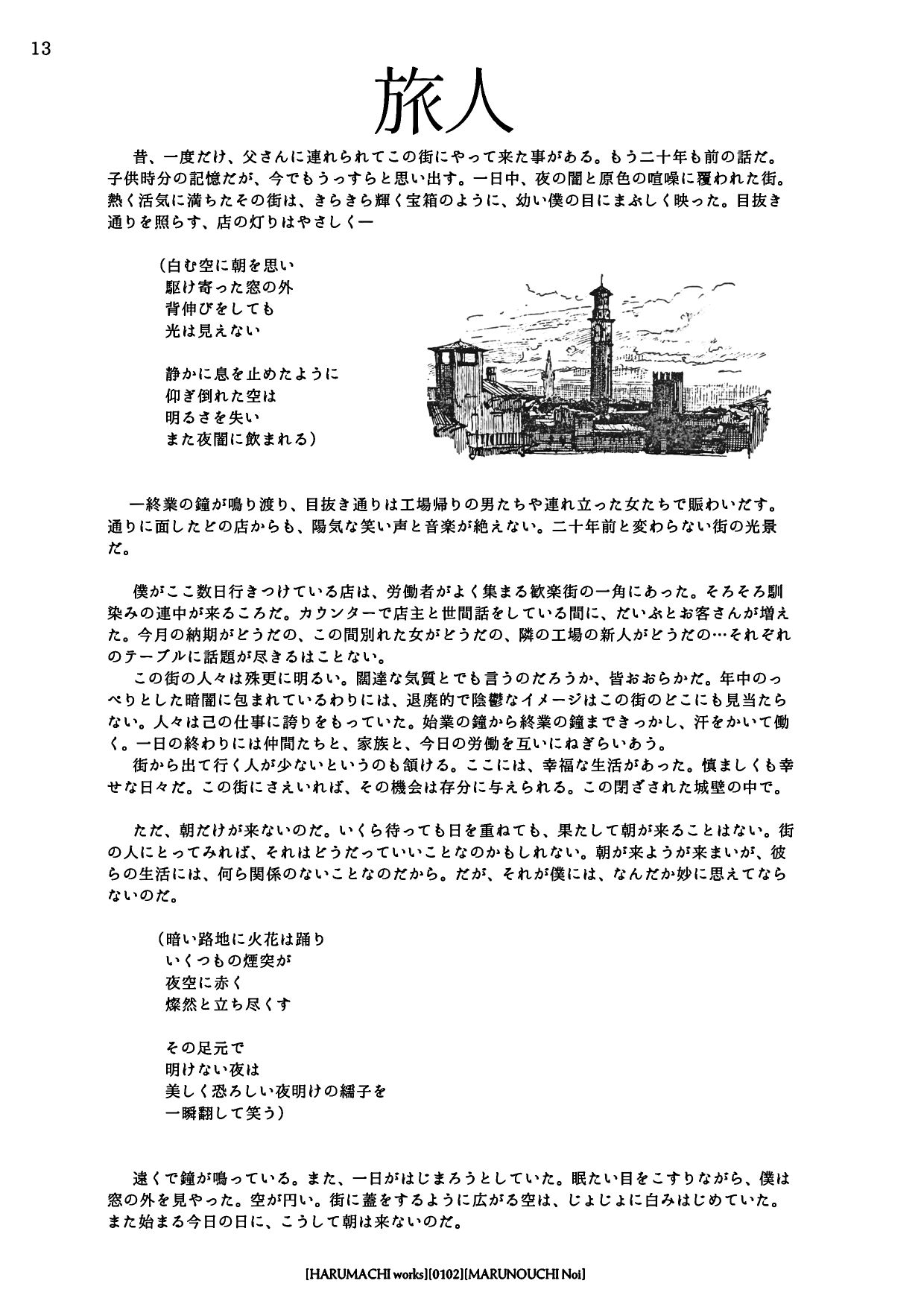昔、一度だけ、父さんに連れられてこの街にやって来た事がある。もう二十年も前の話だ。子供時分の記憶だが、今でもうっすらと思い出す。一日中、夜の闇と原色の喧噪に覆われた街。熱く活気に満ちたその街は、きらきら輝く宝箱のように、幼い僕の目にまぶしく映った。目抜き通りを照らす、店の灯りはやさしく―
(白む空に朝を思い
駆け寄った窓の外
背伸びをしても
光は見えない
静かに息を止めたように
仰ぎ倒れた空は
明るさを失い
また夜闇に飲まれる)
―終業の鐘が鳴り渡り、目抜き通りは工場帰りの男たちや連れ立った女たちで賑わいだす。通りに面したどの店からも、陽気な笑い声と音楽が絶えない。二十年前と変わらない街の光景だ。
僕がここ数日行きつけている店は、労働者がよく集まる歓楽街の一角にあった。そろそろ馴染みの連中が来るころだ。カウンターで店主と世間話をしている間に、だいぶとお客さんが増えた。今月の納期がどうだの、この間別れた女がどうだの、隣の工場の新人がどうだの…それぞれのテーブルに話題が尽きるはことない。
この街の人々は殊更に明るい。闊達な気質とでも言うのだろうか、皆おおらかだ。年中のっぺりとした暗闇に包まれているわりには、退廃的で陰鬱なイメージはこの街のどこにも見当たらない。人々は己の仕事に誇りをもっていた。始業の鐘から終業の鐘まできっかし、汗をかいて働く。一日の終わりには仲間たちと、家族と、今日の労働を互いにねぎらいあう。
街から出て行く人が少ないというのも頷ける。ここには、幸福な生活があった。慎ましくも幸せな日々だ。この街にさえいれば、その機会は存分に与えられる。この閉ざされた城壁の中で。
ただ、朝だけが来ないのだ。いくら待っても日を重ねても、果たして朝が来ることはない。街の人にとってみれば、それはどうだっていいことなのかもしれない。朝が来ようが来まいが、彼らの生活には、何ら関係のないことなのだから。だが、それが僕には、なんだか妙に思えてならないのだ。
(暗い路地に火花は踊り
いくつもの煙突が
夜空に赤く
燦然と立ち尽くす
その足元で
明けない夜は
美しく恐ろしい夜明けの繻子を
一瞬翻して笑う)
遠くで鐘が鳴っている。また、一日がはじまろうとしていた。眠たい目をこすりながら、僕は窓の外を見やった。空が円い。街に蓋をするように広がる空は、じょじょに白みはじめていた。また始まる今日の日に、こうして朝は来ないのだ。
-Download-